こんにちは、「資産ましましブログ」管理人のもりもりもりです。
今回は、現役時代の自分にも教えてあげたかった「警察官の保険」について、実体験をもとにまとめてみました。
警察官という仕事は、他の職業と比べても怪我や病気のリスクが高い仕事です。
私自身、警察学校では毎日のように柔道や剣道、逮捕術などの訓練があり、膝や肩を痛めることもしばしば。現場に出てからも、不規則勤務に夜勤、肉体的にも精神的にもタフさを求められる毎日でした。
だからこそ、多くの警察官が保険に入っています。というよりも、警察学校に入った時点で「半強制的」に加入させられることが多いのが現状です。
でもちょっと待ってください。
その保険、今の自分にとって本当に必要な内容になっていますか?
無駄な保険料を払い続けていませんか?
今回は、「警察共済組合(制度保険)」や「警生協(共済事業)」を軸に、警察官にとって必要な保険・不要な保険、見直すべきポイントについてお話していきます。

この記事を読んで保険を見直すことで年間数万円の保険料が浮くかもしれません!
- 保険に興味がある現役警察官またはその家族
- 家計の見直しを考えている警察官またはその家族
- ライフスタイルが変化した警察官またはその家族
目次
警察官が入る保険にはどんなものがある?

まず、警察官になったらほとんどの人が加入する保険は以下の2つです。
- 警察共済組合(制度保険)
- 警生協(警察職員生活協同組合の共済保険)
これらの保険は、警察学校に入校直後に教務課や教官から「この保険に入ってください」と説明を受けて加入します。選択の余地がほとんどないまま、気づけば保険証が送られてきて、毎月の給与から天引きされるようになっていきます。
特に、警察学校時代は訓練による怪我のリスクも高く、実際に骨折や靭帯損傷をしている同期も珍しくありませんでした。
そう考えると、保険への加入はある意味当然ではあるのですが、問題はその「中身」と「その後」です。

警察官あるある「柔道訓練で骨折して支払われた保険金で新車を購入する人」
在職中、何人かいましたね…
見直しされないまま保険料だけ払い続ける現実

警察官の世界は忙しいです。
配属後も慌ただしい日々が続き、保険の内容を見直す余裕なんて正直ありません。私自身もそうでした。
気づけば結婚して子どもが生まれていたり、マイホームを購入していたり、ライフステージが大きく変わっているのに、保険だけは入校時のまま。
よくあるのが、「若い頃に外部の保険外交員に民間保険を勧められて、よく分からないまま加入してしまう」ケースです。
「共済は簡易的だから、こっちのほうが手厚いですよ」とか、「老後も安心できる終身保険に入りませんか?」みたいな営業トーク、耳にしたことありませんか?
結果的に、同じような補償が共済と民間で重複していたり、保障内容に対して明らかに割高な保険料を払っていたり…。
これ、本当にもったいないです。
共済と警生協は圧倒的コスパ!還付金が大きい

ここで断言しますが、警察共済組合と警生協の保険は、民間保険と比べても圧倒的にコスパが高いです。
理由はシンプルです。
多くの人が知らないんですが、掛けた保険料の3〜4割が毎年還付されるんです。
もちろん、これは毎年必ずというわけではなく、コロナ禍直後のように保険金支払いが多かった年は還付がなかったこともありました。
でも、私の在職中(15年以上)では、ほとんどの年でしっかり還付がありました。
しかも、怪我や病気で保険料の申請をする際の支払いもめちゃくちゃスムーズです。
提出書類も簡単で、私が入院した時も入金までの期間が短かったです。
警察官という職業柄、保険会社からも信頼されていて、過剰請求や詐欺の疑いがほとんどないからかもしれません。
無駄な重複補償を整理しよう

とはいえ、共済と警生協のすべてが完璧というわけではありません。
例えば、以下のような「補償の重複」がある場合もあります。
- 警察共済と警生協、両方で個人賠償責任保険に加入している
- 民間の自動車保険で既に補償されている内容と、共済の補償が被っている
- 警察共済と警生協の補償を合わせると入院時の補償が過剰(一日5万円等)
私が勤務していた県警では、加入保険の一覧表を出力ができるシステムがあったのですが、補償内容の確認が非常に見づらかったです。
だからこそ、自分でしっかり整理しておかないと、同じ内容に二重でお金を払っているなんてことにもなりかねません。
生命保険、独身なら「ほぼ不要」

生命保険についても、思い込みで加入している人が多いと感じています。
「もし自分が死んだら家族が困るかもしれない」
そう考えるのは自然ですが、まず冷静に考えるべきなのは、「自分が死んだときに誰が金銭的に困るか?」という点です。
独身で、実家の両親へ仕送りなどしていないなら、実はそれほど困る人はいません。
警察官には遺族補償年金、葬祭料、弔慰金などの制度がありますので、葬儀代や各種費用はある程度カバーされます。
結婚していても、配偶者が働いていれば大きな保障は必要ないことも。
子どもがいる場合は、遺族年金でカバーできるかをまず確認し、足りない分だけを保険で備えるようにすればOKです。
ちなみに、私の周囲には「とりあえず生命保険は3000万円」みたいに、根拠のない金額で生命保険に加入している人が本当に多かったです。

「何となく不安」、「補償額が大きければ安心」と考えることは危険です!
入院・病気の備えは「貯金」でOK

怪我や病気で入院した場合、働けなくても警察官は3ヶ月程度は給与が支払われます。
さらに、高額療養費制度を使えば、自己負担も(給与額にも寄りますが)月9万円ほどが上限になります。
つまり、ある程度の貯金があればカバーできるんです。
入院中は遊びにも行けませんし、生活費もそれほどかかりません。
「入院に備えて月々3000円の保険料」より、「しっかり貯金しておく」ほうが実は安心だったりします。

貯金がない時は保険で備えて、ある程度貯まったら医療保険はなくても大丈夫です。
仮に掛けるとしても掛け捨てが原則です。
警察共済の積立制度には注意!

ここまで警察共済を手放しで褒めてきましたが、「積立制度」だけはおすすめできません。
私が勤務していた県警では、毎月2万円を上限に年利約1%で積み立てられる制度がありました。
銀行金利が0.01%の時代に1%というのは一見お得にだったので、満額積み立てていました。
でも、あるとき気づいたんです。
「このお金、保険会社が年利7〜10%で運用してるんじゃ…?」
「だったら、自分で運用した方が良くない?」
ということで、全額解約してインデックス投資に切り替えました。
もちろん投資は自己責任ですが、インフレ時代に備える手段としては欠かせない選択肢です。
終身保険・老後の備えは必要か?

警生協では、還付金を自動的に終身保険の掛金に回す制度があります。
でも、これはおすすめしません。
終身保険は費用対効果が非常に悪いですし、老後の医療費は高額療養費制度や1割負担などの公的制度でカバーできることが多いです。
老後に備えるなら、保険ではなく資産形成をしておく方がずっと有効です。
まとめ:保険は「知識」と「整理」が命
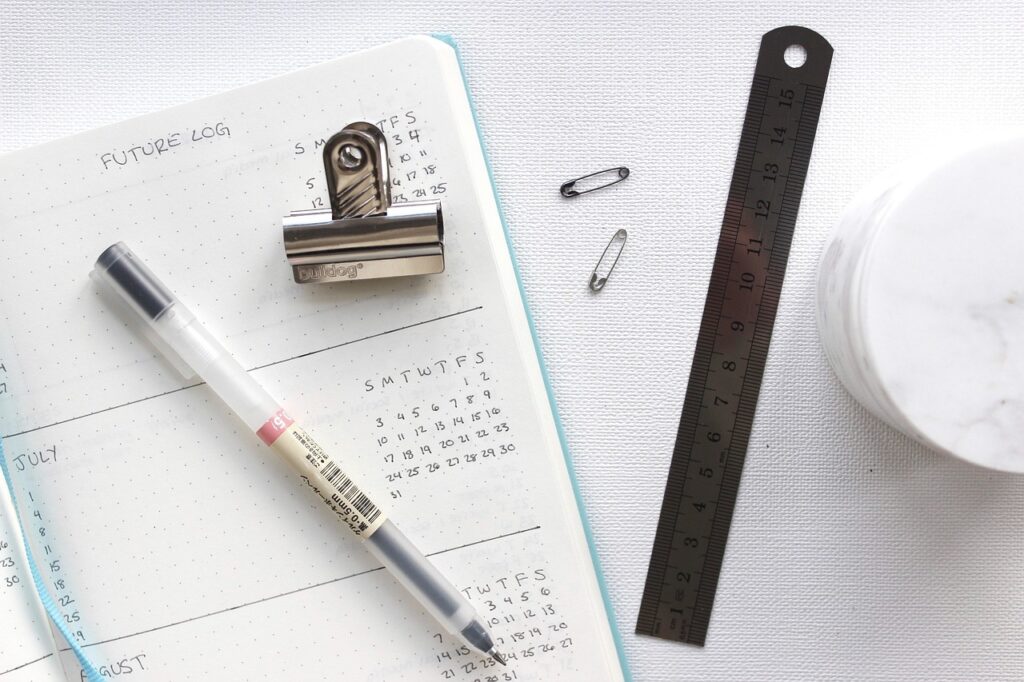
警察官という仕事柄、保険に入ることは自然なことです。
ただし、大切なのは「なんとなく加入してそのままにしない」こと。
- 補償内容が重複していないか?
- 今の家族構成に合った内容になっているか?
- 遺族年金や給与補償の仕組みを理解しているか?
これらを一度見直すだけでも、毎月の保険料をグッと減らせるかもしれません。
浮いたお金は貯金や投資にまわして、将来に備えることができます。
「なんとなく」で入りっぱなしにしている保険があれば、今日をきっかけにぜひ整理してみてくださいね。

この記事を読んで無料のFP相談に行く場合は注意してください。言葉巧みに貯蓄型等の保険会社に利益が多い民間保険へ加入させられる場合がよくあります。




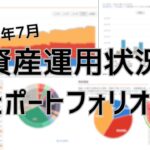
コメント